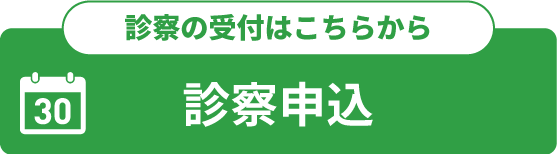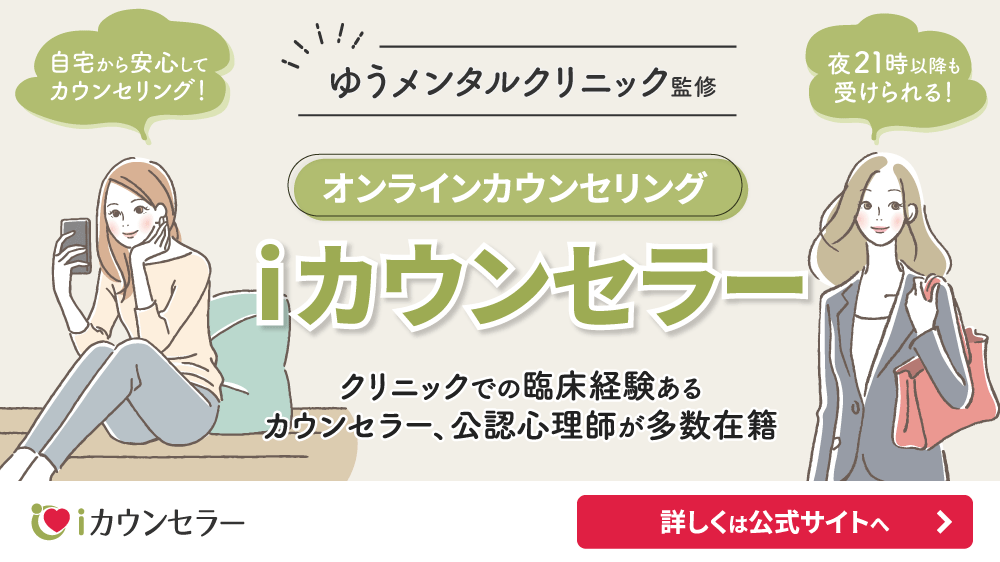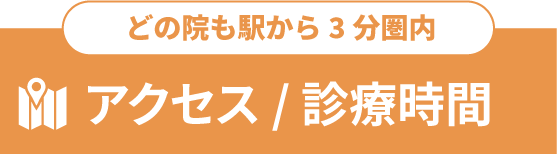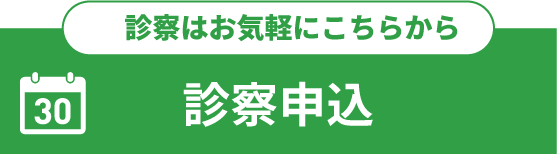産後の三大精神疾患、産褥(さんじょく)期精神病って何?

産後の心の不調を理解し、支え合うために妊娠や出産は、人生における大きな喜びのひとつです。
しかし、その一方で心身に大きな変化が訪れる時期でもあり、時には予想外の心の不調が現れることがあります。
「マタニティブルー」や「産後うつ」という言葉は広く知られるようになりましたが、実は「産褥期精神病」という、より重篤な状態も存在します。
この記事では、産褥期精神病について、医学的な根拠とともに一般の方にもわかりやすく解説します。
もしあなたや周りの大切な人が産後に心の不調を感じているなら、我慢せず、すぐに適切なサポートを受けてくださいね。
産褥期精神病とは?
産褥期精神病(さんじょくきせいしんびょう、Postpartum Psychosis)は、出産後に発症するまれな精神疾患です。
医学的には、500~1000人に1人程度の確率で発症するとされています(Jones et al., 2014)。
この疾患は、非常に重篤な症状が特徴で、迅速な医療介入が必要です。
通常、出産後数日から2週間以内に発症することが多く、まれに数週間後まで遅れる場合もあります。
症状としては、以下のようなものが含まれます。
• 幻覚:実際には存在しない声や物が見える、聞こえる。
• 妄想:現実とかけ離れた強い思い込み(例:赤ちゃんが危険にさらされている、自分が特別な使命を持っているなど)。
• 焦燥感や混乱:落ち着けず、思考がまとまらない。
• 極端な気分変動:極端な高揚感や深い絶望感が交互に現れる。
• 睡眠障害:極端な不眠や、休息が取れない状態。
これらの症状は、突然現れることが多く、周囲の人や本人自身が「何かおかしい」と感じる場合がほとんどです。
産褥期精神病は、放置するとお母さん自身の健康や安全、そして赤ちゃんや家族との関係に深刻な影響を及ぼす可能性があるため、早期の治療が不可欠です。
なぜ産褥期精神病が起こるのか?
産褥期精神病の原因は完全に解明されていませんが、複数の要因が関与していると考えられています。
主な要因として以下の点が挙げられます。
1.ホルモンの急激な変化
妊娠中はエストロゲンやプロゲステロンなどのホルモンが高レベルで維持されますが、出産後、これらのホルモンが急激に減少します。
この変化が脳内の神経伝達物質に影響を与え、精神的な不安定さを引き起こす可能性があります(Bloch et al., 2003)。
2. 睡眠不足
産後は赤ちゃんの世話で睡眠が不足しがちです。慢性的な睡眠不足は、精神的なバランスを崩す大きなリスク要因となります。
特に、産褥期精神病では、極端な不眠が症状を悪化させるケースが報告されています。
3. 遺伝的要因や既往歴
双極性障害(躁うつ病)や統合失調症の既往歴がある女性、または家族にこれらの疾患を持つ人がいる場合、産褥期精神病のリスクが高まるとされています(Jones et al., 2014)。
また、過去の出産で産褥期精神病を経験した女性は、再発のリスクが特に高いです。
4. 心理的・社会的ストレス
出産に伴う責任感、パートナーや家族との関係、経済的な不安など、ストレスが重なることで発症リスクが高まる場合があります。
産褥期精神病の治療とサポート
産褥期精神病は重篤な疾患ですが、適切な治療を受けることで、多くの場合、回復が可能です。
一般的な治療アプローチを紹介します。
- 医療機関での専門的な治療
産褥期精神病が疑われる場合、精神科医や産婦人科医への受診が最優先です。治療には以下のような方法が含まれます。
• 薬物療法:一般的に、抗精神病薬や気分安定薬を使うことで症状を抑え、精神状態を安定させます。
授乳中の場合は、赤ちゃんへの影響を考慮し医師が適切な薬を選択します。
• 入院治療:症状が重い場合、母子の安全を確保するために一時的な入院が必要になることがあります。
一部の病院では、母子同室での入院が可能な「母子ユニット」を備えている場合もあり、赤ちゃんとの絆を維持しながら治療を受けることができます。 - 心理的サポート
カウンセリングや認知行動療法(CBT)は、産後の不安やストレスを軽減するのに有効です。
家族やパートナーも含めたサポート体制を整えることで、回復が促進されます。 - 周囲のサポート
家族や友人、医療従事者によるサポートは、回復の鍵となります。具体的には、以下のようなサポートが役立ちます。
• 赤ちゃんの世話を手伝うことで、お母さんの休息時間を確保する。
• 話を聞く姿勢を持ち、批判やプレッシャーを与えない。
• 医療機関への受診を促し、必要なら付き添う。
「みんな乗り越えてきたから」は危険な思い込み
日本では、妊娠や出産に伴う不調を「我慢するのが当たり前」と考える傾向がまだ残っています。
特に、産褥期精神病のような重篤な状態は、知識が不足しているために「ただの疲れ」「育児のストレス」と見過ごされがちです。
しかし、こうした思い込みは、適切な治療の機会を遅らせ、症状を悪化させるリスクがあります。
あなたは一人ではありません。 産後の心の不調は、誰にでも起こり得るものです。
そして、それは「弱さ」や「母親失格」では決してありません。
医学的なサポートを受けることは、赤ちゃんや家族、そして何よりあなた自身を守るための大切な一歩です。
どうすればいい? 具体的な行動ステップ
もしあなたや周りの人が産褥期精神病の症状に気づいたら、本人と家族の安全を第一に、下記を参考に対応してください。
1 すぐに医療機関に相談する
産婦人科、精神科、または地域の保健センターに連絡しましょう。緊急の場合は、救急外来や精神科救急を利用してください。
2 周囲に助けを求める
パートナー、家族、友人に状況を伝え、具体的なサポート(家事、育児、受診の付き添いなど)を依頼しましょう。
3 信頼できる情報源を活用する
日本産婦人科学会や日本精神神経学会のウェブサイトには、産後のメンタルヘルスに関する信頼できる情報が掲載されていますのでぜひ確認をしてみてください。
また、地域の母子保健サービスも活用できます。
4 自分を責めない
産褥期精神病はあなたのせいではありません。適切な治療を受ければ、必ず回復への道が開けます。
産褥期精神病は、まれですが深刻な疾患です。
しかし、早期に適切なサポートを受けることで、多くの方が健康を取り戻し、赤ちゃんとの新しい生活をスタートさせています。
出産は大きな挑戦ですが、その過程で心や体の不調を感じたとき、それを「当たり前」と我慢せず、勇気を出して助けを求めることが何よりも大切です。
メンタルクリニックは、産後の心の不調に悩むお母さんを全力でサポートします。一人で抱え込まず、いつでもご相談ください。
参考文献
• Jones, I., et al. (2014). Bipolar disorder, affective psychosis, and schizophrenia in pregnancy and the postpartum period. The Lancet, 384(9956), 1789-1799.
• Bloch, M., et al. (2003). Effects of gonadal steroids in women with a history of postpartum depression. American Journal of Psychiatry, 160(5), 924-932.
取材実績(一部抜粋)
【雑誌】マガジンハウス「Tarzan」
【雑誌】株式会社プレジデント社「PRESIDENT WOMAN」
【TV】フジテレビ『バイキング』
【TV】TBS『ビビット』
【YouTube】『ぶーちゃんねる-歌舞伎町リアル-』(
【病院】歩き辛いくらいアトピーがひどいので皮膚科に行ってきました。
)
【YouTube】『かずのすけ』(
敏感肌でもできる【痛くない医療脱毛】はあるの?お肌に優しい脱毛を受け続けたら5年前より若返った30歳男子の『顔脱毛』体験レポ
)
【Web記事】LITALICO発達ナビ
【Web記事】LITALICO仕事ナビ
【Web記事】Medicalook
他多数
森しほへの取材依頼はこちら

ゆうメンタルクリニックは、診察を『24時間・365日』受け付けております!
どんなお悩みも、お気軽にご相談ください。
診察を申し込む
ゆうメンタルクリニックは
全ての院が駅ほぼ0分でフリーアクセス!
お近くの院をお選びください!